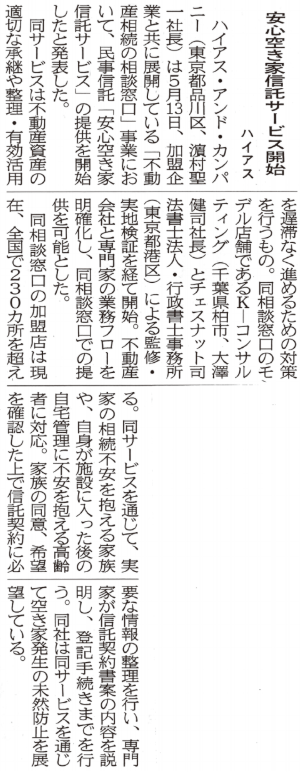住宅新報-令和元年5月21日(火)
安心空き家信託サービス開始
ハイアス
ハイアス・アンド・カンパニー(東京都品川区、濵村聖一社長)は5月13日、加盟企業と共に展開している「不動産相続の相談窓口」事業において、民事信託「安心空き家信託サービス」の提供を開始したと発表した。
同サービスは不動産資産の適切な承継や整理・有効活用を遅滞なく進めるための対策を行うもの。同相談窓口のモデル店舗であるK-コンサルティング(千葉県柏市、大澤健司社長)とチェスナット司法書士法人・行政書士事務所(東京都港区)による監修・実地検証を経て開始。不動産会社と専門家の業務フローを明確化し、同相談窓口での提供を可能とした。
同相談窓口の加盟店は現在、全国で230カ所を超える。同サービスを通じて、実家の相続不安を抱える家族や、自身が施設に入った後の自宅管理に不安を抱える高齢者に対応。家族の同意、希望を確認した上で信託契約に必要な情報の整理を行い、専門家が信託契約書案の内容を説明し、登記手続きまでを行う。同社は同サービスを通じて空き家発生の未然防止を展望している。


- 2019/06/26
- 住宅
- 2019/06/26
- 住宅
- 2019/06/25
- 不動産住宅
- 2019/06/25
- 住宅
- 2019/06/24
- 住宅
- 2019/06/20
- 不動産住宅
- 2019/06/20
- 不動産住宅
- 2019/06/10
- 住宅
- 2019/04/25
- 住宅
- 2019/04/10
- 住宅
- 2019/04/10
- 住宅
- 2019/04/10
- 不動産住宅
- 2019/04/10
- 住宅
- 2019/04/10
- 住宅
- 2019/04/09
- 住宅